備蓄米販売で値下がり
2025年6月25日付の公明新聞に掲載されました。
備蓄米販売で値下がり/コメ流通“見える化”進める/党部会で農水省説明

情報技術、日本の強み生かす
2025年5月24日付の公明新聞に掲載されました。
情報技術、日本の強み生かす/NICTの研究施設を視察/党総務部会

安全・安心にリユース
2025年5月16日付の公明新聞に掲載されました。
安全・安心にリユース/不要品回収、行政と連携後押しを/党懇話会に団体が要望

ケーブルテレビ、IT人材確保必要/党懇話会に連盟
2025年5月16日付の公明新聞に掲載されました。
ケーブルテレビ、IT人材確保必要/党懇話会に連盟

安心の住まい確保を
2025年5月2日付の公明新聞に掲載されました。
安心の住まい確保を/UR賃貸、家賃高騰など窮状訴え/党推進委に団体

万博巨大リング支える
2025年4月19日付の公明新聞に掲載されました。
万博巨大リング支える/集成材の製造施設を視察/福島・浪江町で輿水副大臣

巨大災害から国民守る
2025年4月8日付の公明新聞に掲載されました。
巨大災害から国民守る/富士山降灰や南海トラフ/党部会が議論

政府備蓄米で流通の目詰まり解消を
2025年3月22日付の公明新聞に掲載されました。
政府備蓄米で流通の目詰まり解消を/価格適正化へ実態把握必要/党農水部会、政府に要請

二輪車ユーザーの負担減で要望聴く
2025年3月20日付の公明新聞に掲載されました。
二輪車ユーザーの負担減で要望聴く/党懇話会

認知症ケア技法を学ぶ
2025年3月7日付の公明新聞に掲載されました。
認知症ケア技法を学ぶ/「ユマニチュード」研修会開催/香川・丸亀市

共生社会築く教育充実
2025年3月6日付の公明新聞に掲載されました。
共生社会築く教育充実/認知症巡る出前授業を視察/埼玉で金城、矢倉、輿水各氏

浄化槽の維持管理向上
2025年3月5日付の公明新聞に掲載されました。
浄化槽の維持管理向上/党懇話会、法改正へ骨子案決議

建築設備士確保で団体の要望受ける
2025年2月27日付の公明新聞に掲載されました。
建築設備士確保で団体の要望受ける/党懇話会

(中野国交相に申し入れ)国道6号の渋滞緩和へ整備訴え
2025年2月21日付の公明新聞に掲載されました。
(中野国交相に申し入れ)国道6号の渋滞緩和へ整備訴え/茨城の期成会

かなえられる夢広げて
2025年2月1日付の公明新聞に掲載されました。
かなえられる夢広げて/岡本政調会長、先進の英語教育を視察/茨城・境町

夫婦別姓導入へ議論加速
2025年1月29日付の公明新聞に掲載されました。
夫婦別姓導入へ議論加速/意見集約、与党合意めざす/党推進PTが初会合

(通常国会開幕 公明が両院議員総会)理解・共感得る論戦を
2025年1月25日付の公明新聞に掲載されました。
通常国会開幕 公明が両院議員総会)理解・共感得る論戦を/賃上げ、中小企業、防災対策強化へ予算、年度内成立めざす/斉藤代表、西田幹事長が力説

ふたば支援学校が帰還
2025年1月23日付の公明新聞に掲載されました。
ふたば支援学校が帰還/落成式で輿水副大臣「教育復興へ大きな一歩」/福島・楢葉町に新校舎

認知症の人、創作で笑顔に
2025年1月17日付の公明新聞に掲載されました。
認知症の人、創作で笑顔に/「臨床美術」の効果探る/都内で輿水氏

災害法制に「福祉」を
2024年12月27日付の公明新聞に掲載されました。
災害法制に「福祉」を/能登地震踏まえ識者らと意見交換/党合同会議

(臨時国会閉幕で党両院議員総会)公明が合意形成の要に
2024年12月25日付の公明新聞に掲載されました。
(臨時国会閉幕で党両院議員総会)公明が合意形成の要に/補正予算、政治改革で成果/斉藤代表、西田幹事長訴え

「防災庁」現場の声生かす組織に
2024年12月25日付の公明新聞に掲載されました。
「防災庁」現場の声生かす組織に/災害対応強化策聞く/党合同会議

政治改革、公明案提出へ
2024年12月5日付の公明新聞に掲載されました。
政治改革、公明案提出へ/「政策活動費」廃止を明記/政治資金の透明性確保へ第三者機関を具体化

学びが復興の力に
2024年12月01日付の公明新聞に掲載されました。
学びが復興の力に/「ふるさと創造学サミット」/福島・広野町で輿水副大臣

(臨時国会召集、公明が両院議員総会)政治改革、補正成立早く
2024年11月29日付の公明新聞に掲載されました。
(臨時国会召集、公明が両院議員総会)政治改革、補正成立早く/賃上げで豊かな家計へ/政規法再改正など合意形成の要に

(この人に聞く 公明党の副大臣)福島再生、中長期的に支援
2024年11月25日付の公明新聞に掲載されました。
(この人に聞く 公明党の副大臣)福島再生、中長期的に支援/復興副大臣 輿水恵一衆院議員

栃木県知事が公明に当選御礼/斉藤代表ら応対
2024年11月23日の公明新聞に掲載されました。
栃木県知事が公明に当選御礼/斉藤代表ら応対

(公明、政規法再改正で要綱案)年内成立リード役担う/来週、政党間協議で提示へ
2024年11月16日の公明新聞に掲載されました。
(公明、政規法再改正で要綱案)年内成立リード役担う/来週、政党間協議で提示へ

学校施設の防災機能強化へ支援/公明に中核市市長会
2024年11月14日の公明新聞に掲載されました。
学校施設の防災機能強化へ支援/公明に中核市市長会

生物多様性の保全めざして/COP16の成果と課題
2024年11月12日の公明新聞に掲載されました。
生物多様性の保全めざして/COP16の成果と課題

(衆院選、当選果たした比例5氏が決意)立党精神貫き飛躍誓う/輿水恵一氏(北関東ブロック)
2024年11月03日の公明新聞に掲載されました。
(衆院選、当選果たした比例5氏が決意)立党精神貫き飛躍誓う/輿水恵一氏(北関東ブロック)
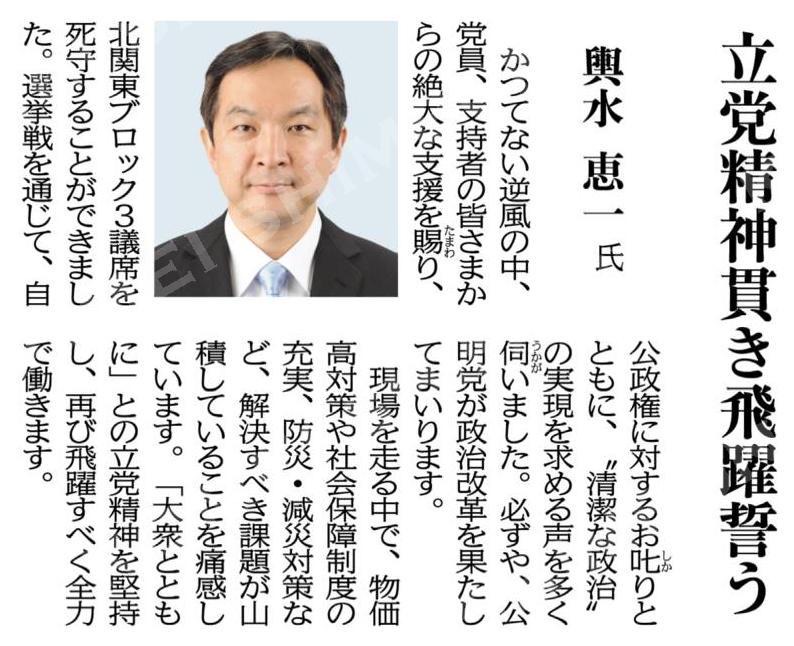
「常磐もの」堪能して!/福島の水産物、魅力を発信/復興イベントで輿水副大臣
2024年11月02日の公明新聞に掲載されました。
「常磐もの」堪能して!/福島の水産物、魅力を発信/復興イベントで輿水副大臣

(15日公示、27日投票)衆院解散、総選挙へ
2024年10月10日の公明新聞に掲載されました。
(15日公示、27日投票)衆院解散、総選挙へ/勢いと団結で勝つ/石井代表ら力説

(認知症施策に全力)運動を独自に考案
2024年10月9日の公明新聞に掲載されました。
(認知症施策に全力)運動を独自に考案/輿水氏、先進的な予防事業視察/埼玉・松伏町

公明党から3副大臣
2024年10月4日の公明新聞に掲載されました。
公明党から3副大臣/輿水(復興)、横山(財務)、鰐淵(厚労)氏

政治資金のチェック、独立性確保した組織で
2024年10月3日の公明新聞に掲載されました。
政治資金のチェック、独立性確保した組織で/党合同会議、中間取りまとめ案議論

(党衆参両院議員総会)衆院選、結束し勝とう
2024年10月2日の公明新聞に掲載されました。
(党衆参両院議員総会)衆院選、結束し勝とう/政策活動費、廃止すべき/公明が自民に提案 旧文通費改革も

(結党60年 党大会で結束し出発)公明「希望の未来」開く
2024年9月29日の公明新聞に掲載されました。
(結党60年 党大会で結束し出発)公明「希望の未来」開く/衆院選 勝利断じて/石井代表、西田幹事長が就任

選挙妨害、適切に対処
2024年9月20日の公明新聞に掲載されました。
選挙妨害、適切に対処/公選法改正 付帯決議案に明記へ/自公実務者が確認

各種団体が公明に政策要望
2024年9月20日の公明新聞に掲載されました。
各種団体が公明に政策要望

建設業のDX推進を
2024年9月18日の公明新聞に掲載されました。
建設業のDX推進を/石井幹事長、埼玉で団体と意見交換会

早期の伴走支援が重要
2024年9月12日の公明新聞に掲載されました。
早期の伴走支援が重要/認知症の集団検診を調査/党推進本部

(選挙掲示板ポスター)品位保持へ規定を新設
2024年9月12日の公明新聞に掲載されました。
(選挙掲示板ポスター)品位保持へ規定を新設/候補者名、記載義務付け/与野党実務者が大筋合意

各種団体が公明に政策要望
2024年9月12日の公明新聞に掲載されました。
早期の伴走支援が重要/認知症の集団検診を調査/党推進本部

(衆院選比例北関東ブロック(定数19) 党予定候補)現場へ動き、声を聴く
2024年9月8日の公明新聞に掲載されました。
(衆院選比例北関東ブロック(定数19) 党予定候補)現場へ動き、声を聴く/輿水恵一 現/デジタル社会へ注力

各種団体が公明に政策要望
2024年9月6日の公明新聞に掲載されました。
各種団体が公明に政策要望

(公明スポット)「二地域居住」普及促す
2024年9月6日の公明新聞に掲載されました。
(公明スポット)「二地域居住」普及促す/企業やNPOの活動を支援/25年度に国交省

(主張)新しい認知症観
2024年9月6日の公明新聞に掲載されました。
(主張)新しい認知症観/当事者が安心できる共生社会に

ポスターの適正化急務
2024年9月5日の公明新聞に掲載されました。
ポスターの適正化急務/公選法改正へ与野党一致


